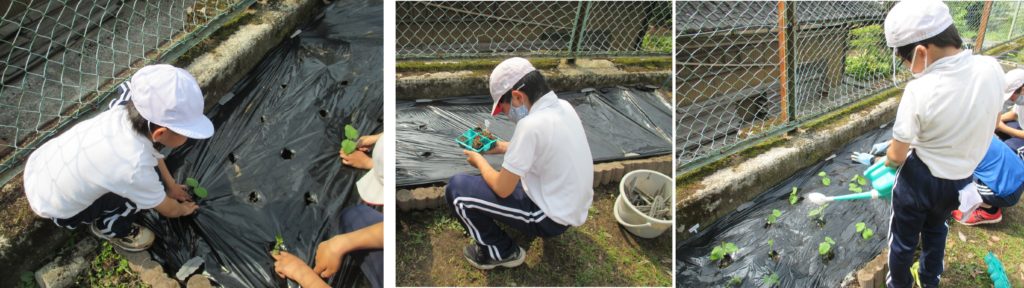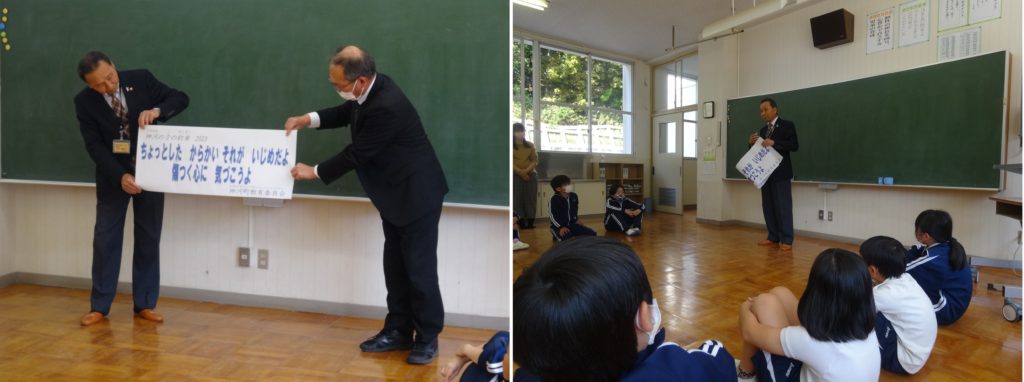家庭教育学級でAED講習会を行った後、救急隊員の方に救急車の内部を見せていただきました。けがをした人や病気の人を運ぶ救急車ですが、中はどのようになっているのでしょう。

病人を運ぶ車なので、中には心電図の器械や気道確保、点滴の準備など病院に運ぶまでの必要な処置ができる、命を救うための道具がたくさん積まれていました。

救急車から、ガシャン、ガシャンとストレッチャーが滑り出てくると、一斉に「お~!!」と歓声があがりました。丈夫で高さ調節ができ、患者さんの容態に合わせてリクライニングの角度も変えることができます。

水の事故に備えた道具もありました。ドクターヘリと救急車の連携プレーで迅速に対応し、いち早く患者さんに対応されている最前線のお話も聞くことができました。みんなの命を守ってくださっていることを実感しました。