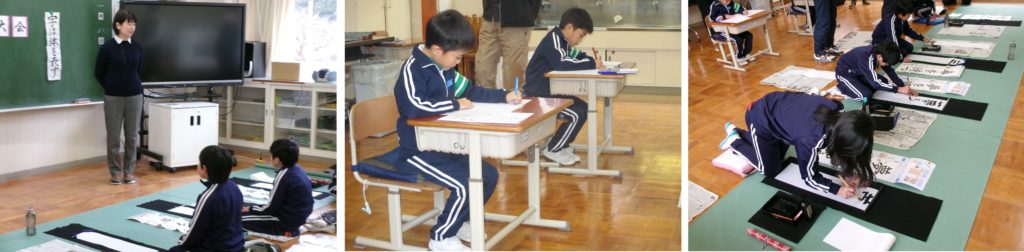来年度に入学予定の園児1名が、小学校の生活を体験するために1年生の教室に遊びに来てくれました。1年生の児童たちはとても嬉しそうに迎え、いっしょに簡単な交流をしました。

1年生の児童たちは、「学校ではこんなふうに過ごすんだよ」と、1日の流れをやさしく教えてあげました。鉛筆の持ち方を教える場面もあり、来校した園児は1年生の話をうれしそうに聞きながら、一生けんめいまねしていました。
短い時間ではありましたが、小学校の様子に触れることができ、来校した園児はにこにこと楽しそうに過ごしていました。1年生にとっても、少し頼もしい姿を見せることができた、温かいひとときとなりました。