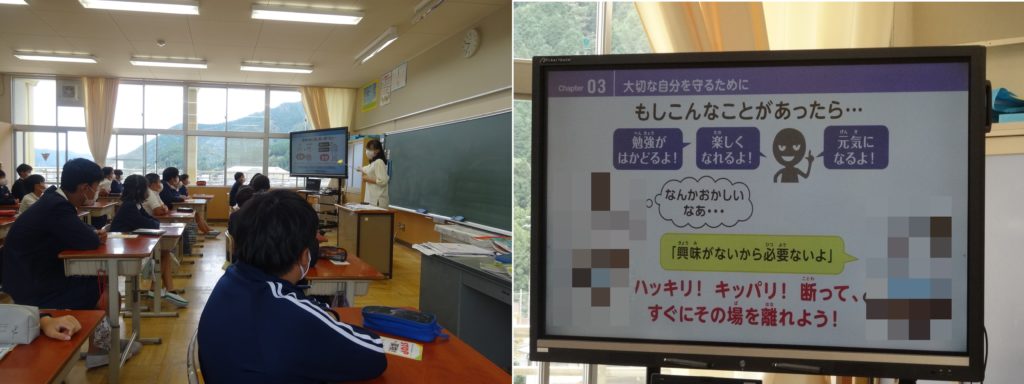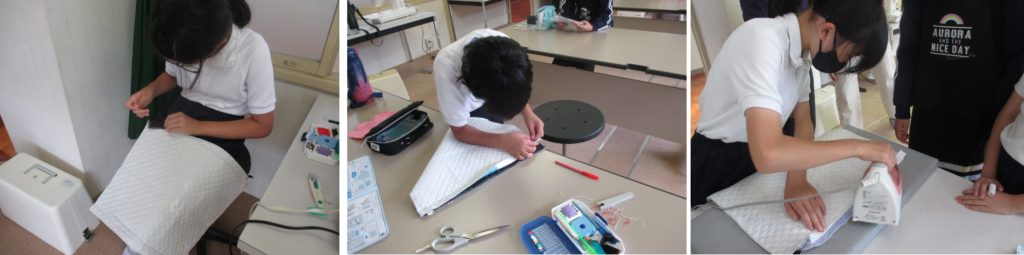1,3年生は夏から虫捕りに夢中で今回の読み聞かせは、その気持ちにぴったりの選書で始まりました。

低学年1冊目は、「アリとキリギリス」こつこつ働くアリの姿と、働かずに食べて歌って楽しく過ごすキリギリスの結末は・・・。2冊目は、イソップ物語でした。子どもたちは、どう感じたでしょう?

高学年の1冊目は、くいしんぼうのオオカミが友だちの家を転々とするうちに、すっかり始めの用事を忘れてしまうお話。2冊目は、おっちょこちょいのお母さんが交通事故で命を落とし、お化けになって子どもを見守る悲しくも、愛にあふれたじ~んとくるお話でした。

秋の夜長ゆっくりした時間に、いい本に出会ってほしいです。