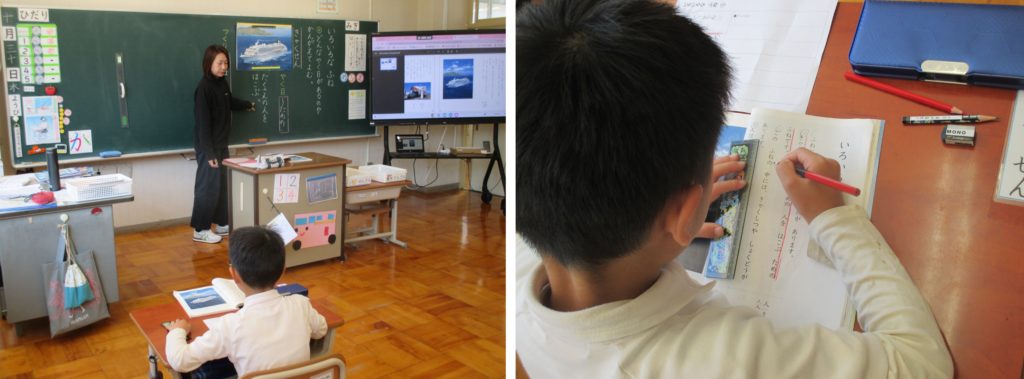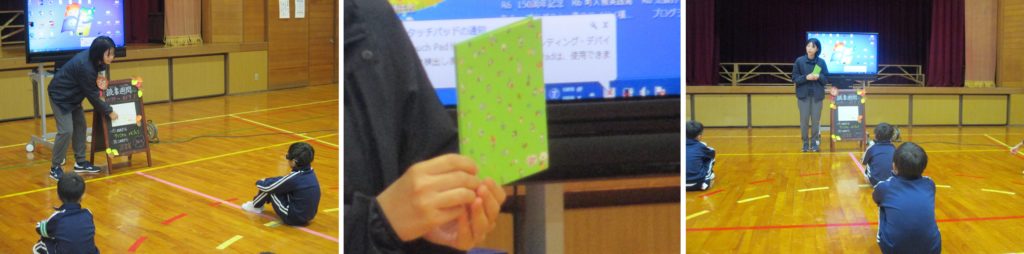長谷小学校に雪が積もりました。今年は例年よりも早い初雪でした。

朝の学校周辺は、一面の銀世界でした。長谷小学校では毎年、年に数回はこうした光景を目にすることができますが、こんなに早く見ることができ、本当に驚きました。

「先生、運動場に雪、積もってるの?」児童も通学前からワクワクしていました。道にある雪を足でかき分けながら、その感触を楽しんで登校していました。学校に着くと、運動場一面に積もる雪に大興奮。「やった、今日は雪合戦や!」と本当にうれしそうでした。

1時間目の体育の後半に、みんなで運動場へ。準備ができた児童から白銀の世界へかけ出し、早速雪合戦の開始です。みんな雪まみれになりながら、運動場を走っていきます。児童も先生もみんな楽しそうに雪玉を投げていきます。一段落した児童の中には、雪だるまを作り始める子も。「どこまで大きくできるかな。」と一生懸命丸めていきます。途中から先生に手伝ってもらいながら、大きな雪だるまを作ることができました。
児童にとって、忘れられない思い出ができた1日になりました。